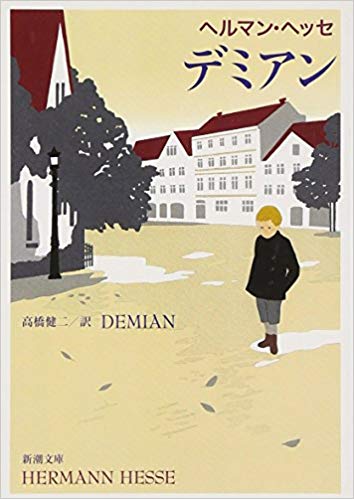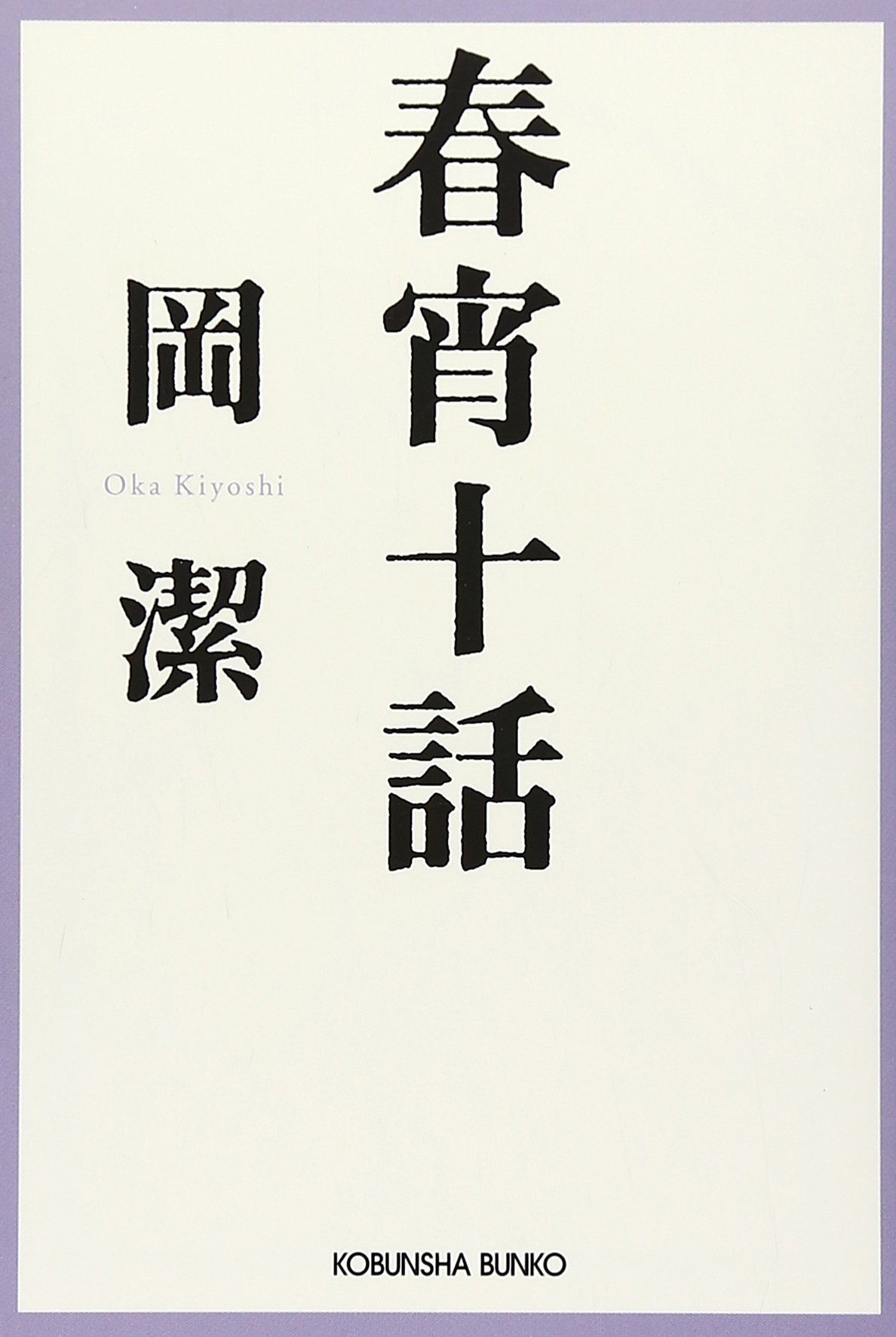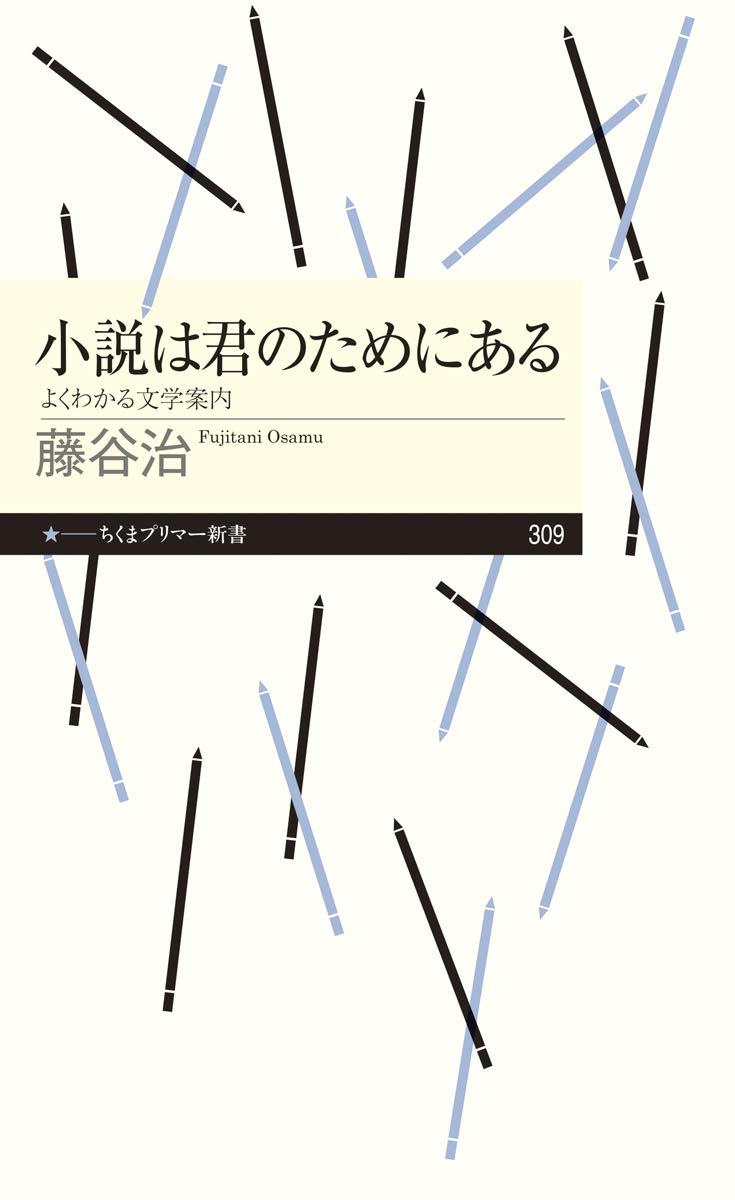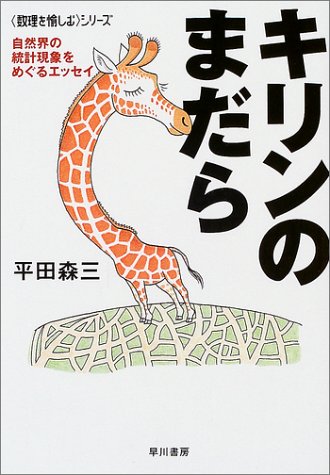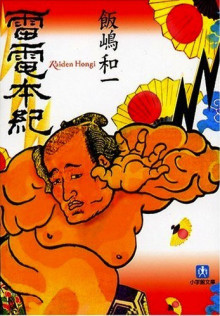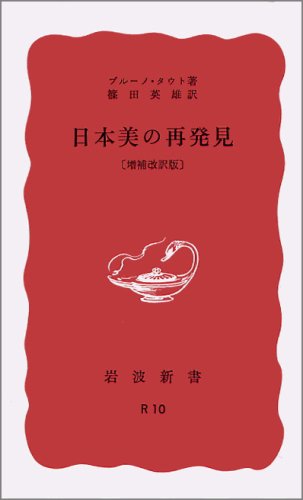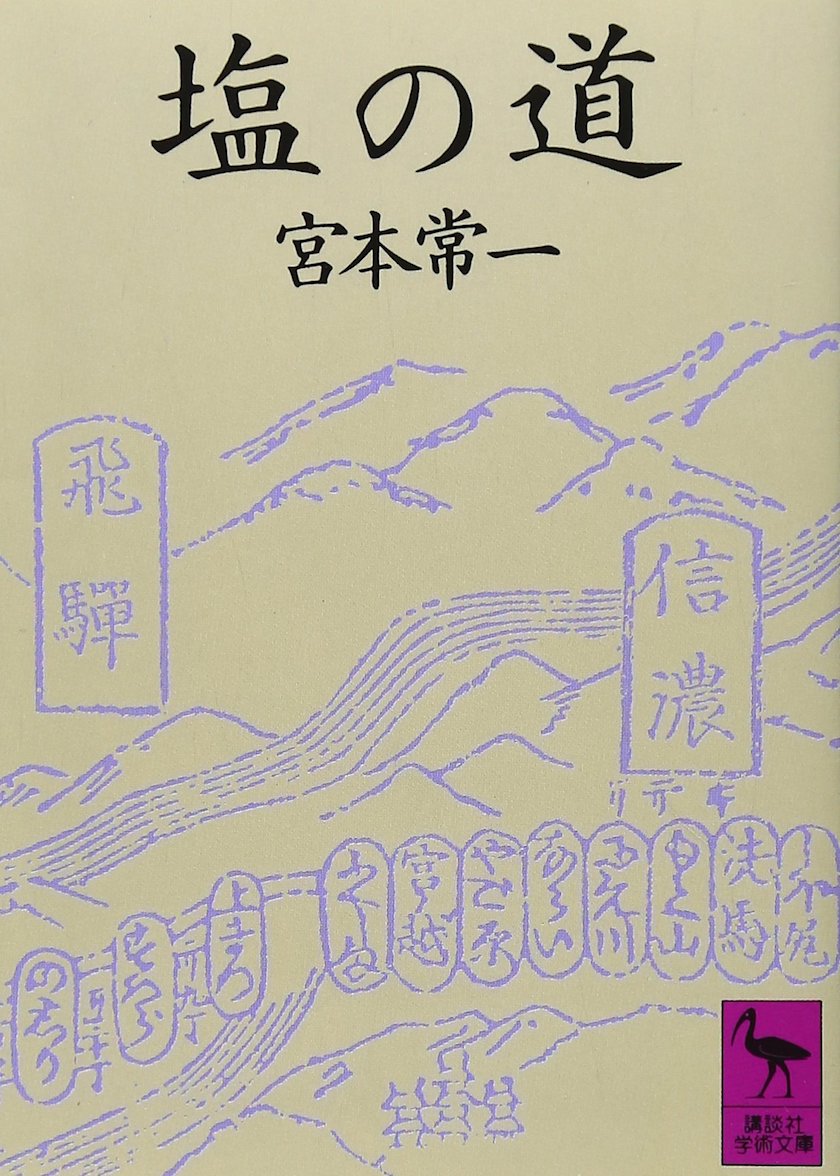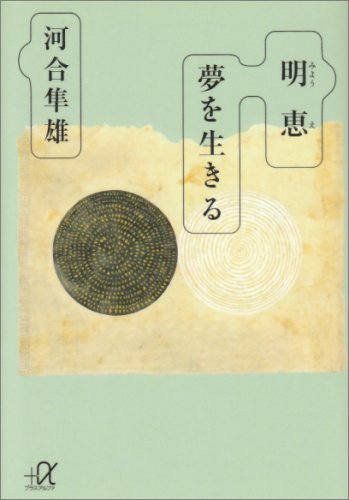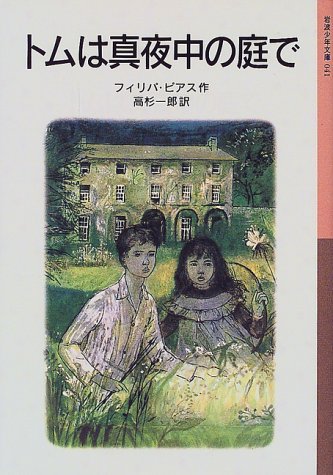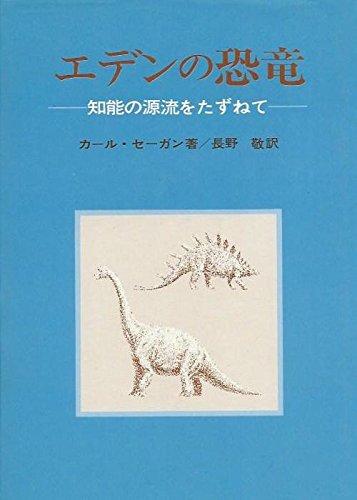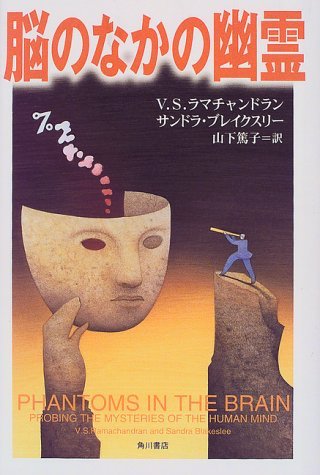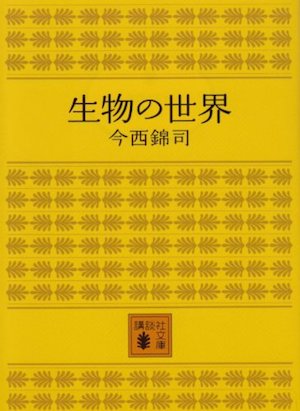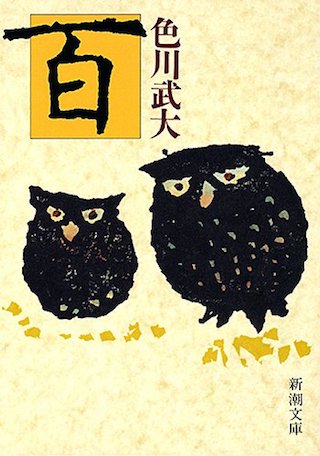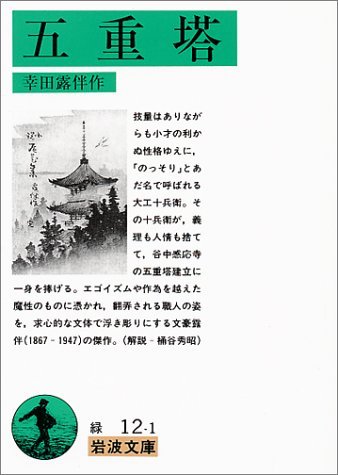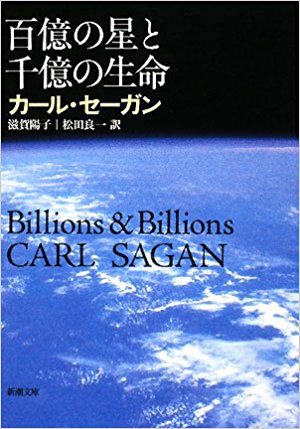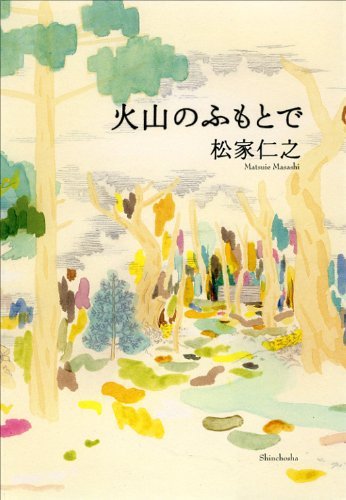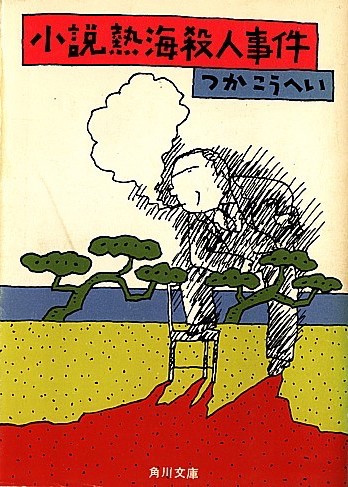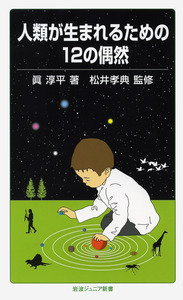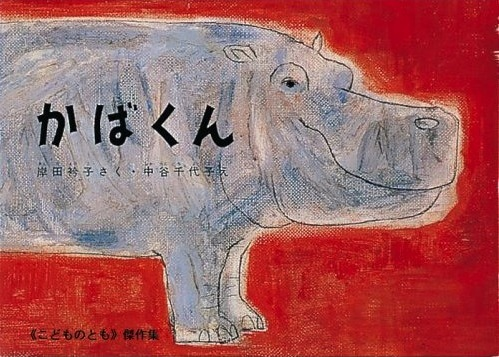「家はなくなったけれど、家に帰りたいの」
泣きながらインタビューに答えておられた被災地の女性の言葉です。
学生の頃、多木浩二の本を背伸びするように読みました。建築家の本には気持ちがまったく入らなかったけれど、『生きられた家』はしみ入るように入った。当時のスケッチブックにもメモが残っていました。
「家は外化された人間の記憶であり、そこには自然と共存する方法、生きるためのリズム、さらにさまざまな美的な感性の基準となるべきものにいたるまでが記入された書物であった」
「このような家は、さまざまな意味において、社会や文化の矛盾、狂気を含む人間の複雑さのメタファーとしてあらわれるものである」
新聞記事の片隅でふと目にする亡くなった人の名前。死と生の境は、ほんのわずかですね。(2017.5.25)